※会計についての学習メモです。
取引先が倒産した時の会計処理は?
ビジネスをしていると、売掛金(まだお金をもらっていない売上)を回収できなくなることがあります。今回は、取引先が倒産してしまい、売掛金1万円が回収できなくなったというケースを例に、会計上の考え方と仕訳について分かりやすく解説します。
売掛金が回収できない「貸倒れ」とは?
会社が商品やサービスを提供したあと、「後払い(売掛)」にしている場合、相手から代金をもらうまでは「売掛金」として資産に計上されます。
しかし、取引先が倒産してしまうと、その売掛金を回収できなくなることがあります。これを「貸倒れ(かしだおれ)」と言い、会計上では損失として処理する必要があります。
貸倒引当金とは?
「貸倒引当金(かしだおれひきあてきん)」とは、将来起こりうる貸倒れに備えて、あらかじめ費用として計上しておくお金のことです。「売掛金の一部は回収できないかもしれない」というリスクを見越して、事前に準備しておくことがあります。
貸倒引当金はお金を用意しておくこと?
→ いいえ。帳簿上での準備です。
貸倒引当金はあらかじめ現金を用意しておくことだと考える人がいるかも知れませんが、それは違います。決算の時に損失を見込んで計上しておき、実際に1万円の現金が回収できない時に「貸倒引当金繰入(費用)」として損益計算書に計上します。またそれと同時に、貸借対照表の負債または資産控除の項目として、「貸倒引当金」として記録されます。お金の動きはなく「会計上で見積り」が行われるだけです。
貸倒引当金をあらかじめ計上する理由は?
貸倒引当金をあらかじめ想定して準備しておくと”何が嬉しい”のでしょうか?
1.利益を正しく見せることができる!
売上があっても回収できない可能性があると利益がでたとは言いづらい。見込みの損失を前もって計上しておけば正確な利益が計算できる。このように正確な利益を出そうとすることを「保守主義の原則」といいます。
2.資産を実態に近づけることができる!
売掛金は本来「お金になる予定の資産」ですが、すべてお金になるとは限りません。あらかじめ戻ってこないお金として差し引いておけば、より現実的な資産額になります。
つまり、貸倒引当金は利益や資産を正しく把握するために設定するのです。
貸倒引当金の仕分はどのようにする?(期末/決算時)
企業は決算時などに、「どれくらい貸倒れが起こりそうか」を見積もって、費用(貸倒引当金繰入)として処理します。たとえば、売掛金が100万円あり、そのうち1万円が貸倒れそうだと見込んだときの仕訳は以下のとおりです。
- 借方:貸倒引当金繰入 10,000円(費用)
- 貸方:貸倒引当金 10,000円(貸借対照表の控除項目)
これにより、将来の損失を前もって利益から差し引いておくことができます。
※期末に貸倒引当金が余った場合は特別な理由がない限りはそのままにする。
※何らかの理由で貸倒引当金繰入を戻す場合は貸倒引当金戻入勘定を使用して利益に戻す。
貸倒引当金の仕分はどのようにする?(発生時)
すでに引当金がある場合は、それを使って処理します。不足分があれば、追加で損失処理をします。たとえば、取引先が倒産し、5万円の売掛金が回収不能に。貸倒引当金が3万円あるときの仕訳はこうなります。
- 借方:貸倒引当金 30,000円
- 借方:貸倒損失 20,000円
-
貸方:売掛金 50,000円
準備していた分(3万円)は使い、足りない2万円は「貸倒損失」として、新たに費用計上します。
貸倒引当金を設定する場合はどのように決めるのか?
過去3年分の貸倒率を平均で求めて決める。例えば、売掛金100万円のうち1%が貸倒れていたら1万円を引当金として計上する。また、取引先の支払いが滞り回収可能性が低い場合は、そのタイミングで貸倒引当金を設定することもある。
今回のケースの概要
-
ある取引先に対する売掛金が 1万円 ありました。
-
しかし、その取引先が 倒産 してしまい、1万円が 回収不能 になった。
-
この貸倒れに対して、すでに 8千円 の貸倒引当金があった。
どのように仕訳するか?(本題)
会計上では、まず準備していた貸倒引当金8千円を使い、不足分の2千円だけを「貸倒損失」として新たに費用計上します。
-
借方(左側)
貸倒引当金 8,000円
貸倒損失 2,000円 -
貸方(右側)
売掛金 10,000円
この仕訳によって、資産である「売掛金」が帳簿から消え、準備していた貸倒引当金と新たな貸倒損失で対応したことになります。
まとめ
貸倒れは、企業活動において避けられないリスクの一つです。だからこそ、貸倒引当金を事前に設定しておくことは、財務の安定性を保つうえで非常に重要です。
今回のように、準備していた引当金で大部分をカバーできれば、新たに発生する損失を最小限に抑えることができます。会計処理を正しく行うことで、実際の経営状態を正しく把握することができます。
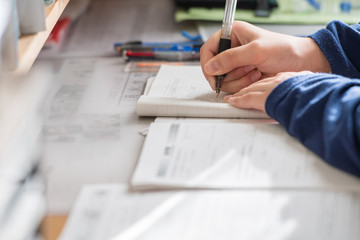


コメント