本屋へたまに行くと本の多さに圧巻する。
最近本屋に行っている?
とりあえず自分の興味がない分野の棚も含めて、興味深いデザインの本の中からとりわけキャッチーな見出しの書籍や雑誌を手に取る。
しかし、出版業界では本は売れないし、本屋も軒並み減っていることが問題になっている。逆に店舗あたりの面積が増えているらしいが、駅前の大型店舗が増えたってことなのか?最近、ジュンク堂や紀伊国屋みたいな大型店舗に行っていないけど、どうなっているんだろう。本屋や出版業界の低迷に関する情報を追っていたら面白い記事があった「書店が増える?その理由とは」お隣韓国では書店が増えているらしい。韓国の元大統領である文在寅も本屋さんはじめて話題になっていたが、独立系本屋さんはなかなかトレンディな商売なのかもしれない。
本屋には本屋の顔がある。店員の顔というよりも、何の本を選んでどう来店した客にそれを魅せるのか?ということで独自性を出せる。客もその独自性を求めていて、価値を感じている。本屋は店頭で価値を提供できるし、それが本の売れ行きに直結する。
未来の本屋はどのようになっているのか?衰退はすれど、大きな駅前の本屋は流石に潰れないのでは。すぐに本が欲しい時に店舗へ行ってさっとその場で買えるのはWebには埋められない利点だと思う。あとは個性ある独立店舗はやっていけるのかもしれないが、それ意外の本屋は趣味でやっているとか古書を扱っているとか特殊な理由がないとやっていけない。
1つ言えることは本屋はたんに本を並べればいいわけでもないし、新しい本や売れる本だけ並べていればいいというものではない。Amazonにはない価値を提供できれば十二分にやっていけるし、客もAmazonにはない価値をリアル店舗に求めている。
本屋大賞などは本屋が作ったランキングで普及しているし、あれをもとに本を買う人も多いだろう。ただこれが店舗で買う人が増えたかと言われるとそうでもないのではないか。例えば本や独自の本屋大賞をつくりだしてアウトプットするような、客と極めて近いところで対話するようなコミュニケーションがないと面白くないのではないか。
本屋をWebにつくるには?
リアル店舗をWebに置き換えるという観点で考えるといろいろな課題が出てくる。そもそも3D空間を2D平面に置き換える時点でまったく異なる。2Dを3D化してVRにする手もあるが初戦は2Dの延長に過ぎない。
それで以前にも本の表紙って出版社に著作権があるので画像転用したら指摘されて下手すりゃ訴えられるんだっけ?ということを調べていた。結構、画像を表示していない電子書店が多いことから画像を使い回すと指摘されることは、想像に難くない。じゃあ、書店サイトからリバースプロキシサーバで児童取得すればいいか。やっていること漫画村と同じだな(汗)。
書籍の表表紙を何パターンか作って自動生成すれば著作権を侵害せずにどうにかそれっぽいサムネイル画像が量産できるのでは。それこそ、生成AIの出番かもしれない。同じような色合いだけど、フォントも違えば微妙に色々と違えば出版社も著作権侵害だとは言えないはず。著作権の根拠が法的にどこにあるのか謎。
創作性の有無が著作権の根拠になるならテンプレ化した疑似表表紙は創造性を流用したものではない。そもそもパターン化されてそれっぽい時点で創作性がない。イラストはイラスト屋の画像で置き換えればいい。そもそも嘘っぱちの書籍表表紙を作り出すな!と客や出版社に指摘されるかもしれない。客が言うならまだしも出版社がそれを言うなら、もともとの画像を使わせろって話だ。逆にこの不満は、何らかのかたちでコンテンツなり付加価値に昇華する方法はあるかもしれない。
でも、表紙をパクってもパクられた書籍であって、それがオリジナルに並べるのって色彩とレイアウトの一部であって、例えば「著者の顔」みたいなものをイラスト屋に置き換えてもうさんくさい。逆にまがい物感が表に出すぎて、誰の評価も得られないものになる。⋯前途多難。
また、時間がある時に考えてみるが、拡散するだけで「望ましい答え」にたどり着ける気がしない。
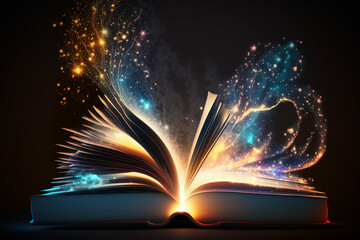


コメント