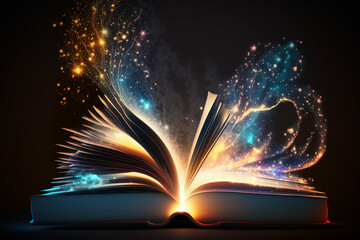※この記事は執筆中です。「雑歴史について(はじめに)」
日本史
日本史の総論
「旧石器時代の総論」「旧石器時代の総論」「弥生時代の総論」「平安時代の総論」「鎌倉時代の総論」「室町時代の総論」「戦国時代の総論」「安土桃山時代の総論」「江戸時代の総論」「明治の総論」「大正の総論」「昭和の総論」「平成の総論」「令和の総論」
日本史の歴史的事件簿
「日本史の歴史的事件簿」…日本史の事件のみを羅列したメモ
日本のすごい人一覧
ひみこ(卑弥呼)
・邪馬台国の女王。魏の皇帝から「親魏倭王」の号を与えられた。魏には奴隷や布を貢物として送った。邪馬台国と狗奴国(くなこく)が争った際は魏から使者を狗奴国に送った。卑弥呼の死後は13歳の伊予(いよ)を女王にした。邪馬台国があったのは北九州や奈良にあったと言われているが正確な位置は今もなお不明。
継体天皇(けいたいてんのう)
九州の豪族磐井を倒して大和政権の国内統一の基礎を築いた。大伴金村(おおとものかなむら)や物部麁鹿火(もののべのあらかひ)の支持で507年に天皇に即位。
磐井(いわい)
筑紫国(つくしのくに)の豪族。朝鮮飯能の新羅に敗れた任那(みまな・にんな)を助けるため、継体天皇が出兵を命じたが逆に新羅と手を組み九州の火国(ひのくに)・豊国(とよくに)とともに近江毛野軍を迎え撃つも1年半続いた戦いに敗れた。
蘇我馬子(そがのうまこ)
敏達天皇(びだつてんのう)が即位した時に大臣(おおおみ)に任命。日本の神を信仰する物部氏に対して仏教を広めた。物部守屋(もののべもりや)を滅ぼした。法興寺(飛鳥寺)を完成させ仏像を安置した。石舞台古墳は蘇我馬子の墓と言われている。