縄文時代は今から1万数千年前から1万年続いた時代。
人々は、縄目模様の縄文土器を使用。竪穴式住居に住んでいた。動物や魚や貝を食べて暮らしていた。狩猟採集生活から定住生活に変わっていった。縄文時代の前は打製石器が使われていたが、磨製石器が使われるようになった(どちらも石ころだが、打製石器は石を石で割って刃をつけ、磨製石器は石を磨いたもの)弓矢なども使われるようになった。貝塚を調べることで、何を食べていたか分かる。植物もブナやカシなどの食べられる実がなる森が広がった。土器はカシの実を煮てアクを抜くために使われた。
黒曜石はマグマから生まれた天然のガラスである。他にも割れると角が鋭くなる性質の讃岐岩(サヌカイト)が打製石器の作成に用いられた。
E・D・モースは大森貝塚から食人(カニバリズム)の証拠を見つけた。
人々は屈葬されていた(屈葬とは、体を折り曲げて埋めること)。赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる格好だという説もある。遺体を焼かず土葬する)また、遺体に赤い鉱物の粉がかけられていることがあった(生き返る呪いと言われている)。石を抱えて埋められることもあった(抱石葬)。
竪穴式住居にも種類があり、大型竪穴式住居、大型掘立柱建物、掘立柱建物などがある。青森県の三内丸山遺跡にあるものが有名。ひとつの集落は2,30人のものが多いが、三内丸山遺跡は数百人規模の集落跡である。
黒曜石は武器を作ることに使われた。翡翠(ひすい)は勾玉などの装飾品を作成するのに使われた。黒曜石や翡翠は産地が決まっていて、一部の地域から数100Kmも運ばれたことが分かっている。
人間が犬を飼い始めたのは1万年前から3万年前。犬の土偶や埋葬された犬が見つかったことから人に大切にされていた。
珍しい土偶は国宝土偶と呼ばれている。遮光器土偶、中空土偶など女性に見立てたものが多い。縄文中期の火焔型土器の装飾は複雑な模様として美術的な価値が認められている(芸術家の岡本太郎が太陽の塔のモチーフにしたことで有名になった)。
3000年前のエジプト文明にファラオ王がいた時期に日本は縄文時代だった。ピラミッドの建設、ストーンヘンジなどが造られた。中国では漢字の元になった甲骨文字が生まれていた。
阿智県豊橋市牛川町で見つかった人骨は3万年前のもので牛川人(うしかわじん)と名付けられたが日本人と異なった特徴を持つ。静岡県三ヶ日町で見つかった人骨は三ヶ日人(みっかびじん)と名付けられたが牛川人よりも新しく1万年前のもの。兵庫県明石市の海岸で見つかった人骨は明石原人(あかしげんじん)というが50万年ころのものである。
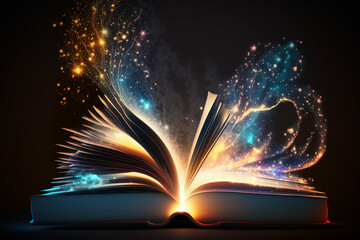


コメント