石原慎太郎とは何者か?時代的普遍性がないのはなぜか?
⋯そもそも石原慎太郎という男を私はまるで知らないのだが『男の業の物語』を読んでいる。
そもそも私は石原慎太郎という男をまるで知らないのだが、今『男の業の物語』を読んでいる。
「男の最高の美徳とは何か?」という問いについて、三島由紀夫との対談で「自己犠牲」で一致した、というくだりが気になって。自己犠牲についてはまた別の記事で書こうと思うが、石原慎太郎のエッセイや振り返りは何本か読んでいて、ふつうに安藤昇や花形敬といった伝説的なヤクザたちと交流があったことなど、面白い話も多い。
石原慎太郎世代はほとんど鬼籍に入られてしまったが、当時を知る人に「石原慎太郎をどう思っていたか」と聞く機会も、今となってはなかなか得られない。なお、安藤組などのヤクザも、もとは今の「しばき隊」的な存在として登場したらしい。
──それはそれとして、ふと思ったのだが、石原慎太郎は結局、同世代とその前後にしか支持されていない。少なくとも現代の若者から振り返られるような人物ではない。それはなぜか? 時代的な普遍性がまるでない作品だからだろうか。
もちろん、時代を超えた作品が常に優れているわけではない。だが、私のように後の世代の人間が彼の作品を後追いで読むとなると、やはり時代を超えて通用する作品の方が手に取りやすい。
──というわけで、「石原作品は時代を超えて面白いものではないから振り返られないのではないか?」という仮説を立ててみたのだが、果たしてどうだろうか。
ChatGPTによれば、石原慎太郎は戦中派であり、戦後の「平和主義一色の風潮」に対して疑問を抱いていた人物で、「国家の誇り」や「自立の意義」を強く主張していたらしい。そうした姿勢は、下の世代──たとえば反体制的な団塊世代──とは相容れず、そもそも反りが合わなかったという。
石原慎太郎と前後の世代の思想を比較してみる
私の独断と偏見で少しは興味がある人と少しは知っている人になりがちだが比較してみる。年代はあくまで思想形成の一因に過ぎないが、おおよそどの時代を生きたのか整理するのにはとても役立つにもかかわらずこの手の情報を図示化してくれている資料はあまりないのではないか。
そーいえば養老孟司(1937)が言っていたが、戦争世代の人(戦争に行った人or戦争に行かなかった人)、戦争の時に学生だった人(戦役逃れの三島or小学生の養老)、戦後に生まれた人は細かくカテゴライズするとよいとか言っていたような⋯というわけで5つにカテゴライズしてみた。
戦中戦後世代を年代別に5つに区切る
・戦争兵士世代(1900~1926年)
→ 司馬遼太郎(1923)、水木しげる(1922)、大岡昇平(1909)
・戦争文化人世代(1900~1926年)
→ 小林秀雄(1902)、丸山眞男(1914)
・戦中青年世代(1927~1935年)
→ 三島由紀夫(1925)、手塚治虫(1928)、江藤淳(1932)、石原慎太郎(1932)、吉本隆明(1924)
・戦中少年世代(1935~1939年)
→ 養老孟司(1937)、大江健三郎(1935)、小田実(1932)、宮崎駿(1942)
・戦後世代(1940年以降)
→ 富野由悠季(1941)、宮崎駿(1942)、村上春樹(1949)
太宰治、三島由紀夫、石原慎太郎の年齢差
・太宰治(1909)戦前の市民的退廃/弱さ
→ 三島由紀夫と16歳差
・三島由紀夫(1925)美・国・武士道への陶酔
→ 石原慎太郎と6歳差
・石原慎太郎(1932)
その他、覚書。
・吉本隆明(1924)戦後リベラル
・手塚治虫(1928)反戦平和主義
・宮崎駿(1942)軍国主義少年&反権力
・大江健三郎(1935)戦後リベラル
・さいとうたかを(1936)国家と個人/正義と暴力『ゴルゴ13』
・富野由悠季(1941)国家と個人/理想と現実
・水木しげる(1922)戦争体験漫画
・白土三平(1932)『カムイ伝』
※三島由紀夫と石原慎太郎の間に手塚治虫がいるが、2人とは対象的な戦後的平和主義思想の漫画家であるのが意外だった。
※漫画の由来が風刺(批判精神の表現)を目的のためか、リベラル寄りにならざるを得ないのかもしれない。
※滅びの美学とか英雄精神が三島由紀夫に通じるとして挙げられたのが永井豪と松本零士だが政治思想とはちょっと違う気がした。
※Chat-GPTが出してきた小林よしのりは、保守というよりリベラルだろう⋯知らんけど。
まとめ
⋯というわけで、世代を超えて右も左もいるのだが、三島由紀夫(1925)あたり”1926年前後”が分水嶺というか特異点というか正規分布の中央盛り上がり部分という感じで捉えると戦後文学や創作の立ち位置が明確になってくるのかもしれない。
補足と駄文
西部邁(1939)は左翼思想から保守思想へ転向。西尾幹二(1947)は保守思想。渡部昇一(1930)は保守思想。田原総一朗(1934)。渡部昇一が保守思想を持つのは自然だが、西尾幹二はなぜ戦後に保守思想の論客になったのか?
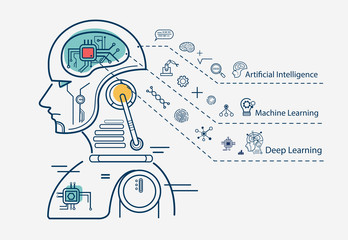


コメント