あらゆる仏典は悟りを得るためのヒントになるものだ。
…と好意的に解釈するものだと思っていたので些細は矛盾は気にしなくていい。
そんなふうに私は捉えていたが『ブッダという男』ではそういう解釈は誤りだとされている。
一部の仏教学者は『形而上学』や『経験論』などという仏典にはない用語を持ち出して、「ブッダは経験論者の立場から形而上学的な自己を否定したが、完成された真実の自己の存在を認めてみた」などと主張し、仏典の矛盾を調和している。
まあこれは仏教学者の解釈だよなーと思うが、一切のものは自己ではないという自己と、自己を愛せの自己は違うものだよね。で済む話だ。
調和させるならば、初期仏典のなかにある言葉で調和させるべきである。初期仏典のなかでブッダは、自己原理(アートマン)を連想させる真理は、世間の習わしに従って用いているにすぎないと述べている。つまり、ブッダが「自己を愛せ」などと表現する場合の”自己”とは、世間の習わしに従っているだけで、恒常不変の自己原理が想定されているわけではない。
というわけで、結構この本については真っ当なことが真っ当に書かれている。
アカハラの話に興味を覚えて手にとったが、別に「私の仏教観」が害される部分は特にない普通の人からすると無害な仏教の解説本である。
最初はセンセーショナルな仏教解説本だ!と思って読むが、まあ「そりゃそうだよね」と思うところが多くて、原始仏教を正しく知ることができるというだけで「おどろくところ」は特にないなという感想に落ち着いてくる。


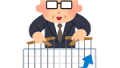
コメント