個人に権利と自由が与えられた近代の確立とかいう幻想。
近代科学はキリスト教の権威に基づく主観ではなく人間の理性による客観を重視した。観察と実験を通じて数学的思考を用いて自然を理解しようとした。ただキリスト教的な動機はあり神の偉大さを確認するために科学が発展した。
カトリックの聖職者コペルニクスは古代ギリシャにプトレマイオスが唱えた天動説を否定した。『天体の回転について』を著し地動説を唱えた。イタリアのガリレオ・ガリレイは天体観測の結果、コペルニクスと同じ結論に達した。『天体対話』を著したが教会から異端審問による宗教裁判で有罪判決を受けて「それでも地球は動く」と言ったという。ドイツのケプラーも地動説を支持した。
イギリスのニュートンは万有引力の法則と微積分法と光のスペクトル分析の三大発見をした。『プリンキビア』(自然哲学の数学的原理)を著した。
イギリスの経験論
イギリスでは経験論が産まれた。経験によってのみ得られる事実を重視した。経験論者であり科学者のフランシス・ベーコンは「知は力なり」と考え自然を支配して利用しようと考えた「自然は、服従することによってでなければ征服できない」と述べた。ベーコンはイドラ(ラテン語で迷妄や幻像の意)を種族、洞窟、市場、劇場に分類して先入観を避けて帰納法を重視=観察や実験から得られた個人的事実を整理し、一般法則を発見しようとした。『ノブム=オルガヌム(新機関)』を著した。
ホッブズは機械論的唯物論を唱えた。人間知識は記憶により快と不快を判断する。「人間は内部の意思を自由に働かせれて行動しているわけではなく、経験に由来する外部の知識が意志を決定する」と考えた。ロックは経験論を確立した人物で『人間悟性論』を著した。人は産まれた時に白紙(タブラ・ラサ)であり、観念は経験に基づいて構築されたとして生得観念を否定「人間の理性は経験なくして働き得ない」と考えた。
バークリー「存在することは知覚されること」と唯心論を唱えた。ヒュームはロックの経験論を徹底させて「原因と結果に因果律はなく、人間は知覚の蓄積から推論しているだけ」という懐疑論の立場(言い換えれば徹底した経験論)を『人性論』で著した。人間を「知覚の束」と呼び人間も主体として存在すると考えられる根拠はなく、ましてや世界が精神の外に独立して存在すると確信できない。あるのは感覚の集まりに過ぎず経験で得られる以上の知識は存在しないと考えた。
大陸合理主義
ヨーロッパでは合理的に真理を導く合理主義が産まれた。
フランスのデカルトは「コギト・エル・スム」(ラテン語でわれ”思うゆえに我あり”)を唱えて考える自分を哲学の第一原理と位置づけた方法的懐疑を唱えた。『方法序説』『省察(せいさつ)』『哲学原理』を著した。また物心二元論を説いた。ベーコンの帰納法に対してデカルトは演繹法を使った。
オランダのポルトガル系ユダヤ人であるスピノザはデカルトを独学で「学び世界のすべては神のあらわれ」という汎神論を説いた。事物と精神を神による一元論「神即自然」と考えた。『エチカ』を著した。
ドイツのライプニッツは事物の究極的要素は神が創ったモナド(量子)であると考え『単子論(モナドロジー)』を著した。偶然が入り込む余地を否定し経験論を否定する合理論を唱えて一元論を打ち出した。なおニュートンとライプニッツは仲が悪かった。
科学革命
イギリスの歴史学者バターフィールドは17世紀の近代科学の設立を科学革命と名付けた。
アメリカの科学哲学者トマス・クーンはパラダイム論を唱えた。自然とは目的が先にあるという目的論的自然観を説いた。これに対してデカルトは自然は機械的な物体の運動だと考え機械的自然観を説いた。これを「自然の数学化」とも呼ぶ。
アリストテレスの影響を受けた中世カトリック教会のスコラ哲学の世界観から近代の数学や物理の発展の源泉として占星術、魔術、錬金術といったルネサンスの神秘主義もある。
進化論
イギリスのダーウィンは生物進化論を説いて『種の起源』を著した。ダーウィン「人間を含めた生物は突然変異と自然選択に基づいて環境に適応することにより、系統的に文化して多様なものになっていく」。
ダーウィンの進化論はイギリスのスペンサーにより社会進化論へと発展した。社会や国家も適者生存の原理に基づいて進化していくと考えた。弱肉強食や優勢劣敗という言葉はスペンサーが考えたという。
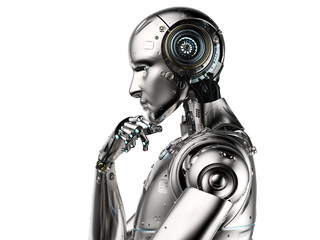


コメント